

4月も中旬に差し掛かり、新入社員たちが少しずつ職場に馴染み始めてくる時期。
しかし、慣れた頃だからこそ、浮き彫りになるのが「育成体制」の課題です。
今回は、「OJT担当者だけに丸投げしがち」な現場で起こる問題と、その解決のヒントを含めた
「新人育成において中堅社員をどう巻き込むか」というテーマでお伝えします。
OJT担当者にすべて任せるのは危険信号?
多くの企業では、OJT担当者(教育係)を決めて、新入社員の育成を行っていますね。
一見合理的に見えるこの仕組みですが、担当者が不在のとき、誰に何を聞けば良いのか分からなくなるなど、
新入社員の“安心の拠り所”が1人しかいないことのリスクも抱えています。
そこで鍵になるのが、「中堅社員」の存在です。
OJT担当者でなくても、日常的に近くで働いている先輩社員が、「あの人がいないから分からない…」という新入社員の不安を
さりげなくフォローできる体制が望ましいのです。
とはいえ、育成は本来の業務に加えての追加作業。
中堅社員にとっては「なんで私が…」と思ってしまうこともあるでしょう。
ですが、「人を育てることは、自分が育つこと」にも繋がります。
「Aの説明で伝わらなかったなら、Bの説明を試してみよう」
「伝え方を工夫することで、提案力やプレゼン力が磨かれていく」
そうした視点で新人育成に関わると、それが自分のスキルアップやキャリア形成にもつながっていくのです。
“育成係だけ”に任せない職場の空気づくりを
育成担当者に新人育成を任せるとき、会社側は「フォロー体制」も一緒に整備すべきです。
たとえば、
- 育成担当者の他に、質問できる先輩の存在を明示する
- 担当者の負担を減らすために、業務量を調整する
- チーム全体で「新人が育つことは自分たちの成果になる」という意識を持つ
このような体制が整えば、育成担当者だけでなくチーム全員が「教育に関わっている」という感覚を持てるようになります。
配属ミスや教育のズレを放置しないことも大切
良い人材を採用しても、適切な配属がされなければ、その力は発揮されません。
現場で「この人はここでは生きないかもしれない」と気づいた場合は、
人事や上司と連携して再配置を検討することも必要です。
新人が「合わない」と感じる前に、大人側が察知して対応する。
そうした感度の高い組織づくりも、育成の質を高める鍵となります。
育てることは、自分が一番成長できる経験
新人を教えるのは、難しいし根気もいる。
だけど、自分が分かっていると思っていたことを「人に伝える」という行為は、
自分自身の理解をより深めるチャンスでもあります。
それはまさに、「育てながら育てられる」経験。
親が子に言うように、「育てられているのは自分なんです」と気づけたとき、
育成という仕事に、やりがいと意義を感じられるようになるのです。
新人育成を個人の仕事にせず、チーム全体で関わる。
教える人も育つし、会社の土台も強くなる。
新人にとっても安心できる環境が整う。
この時期、多くの職場で始まる新人との関わり。
ぜひチームの一員として、また自分の成長のチャンスとして、育成に一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
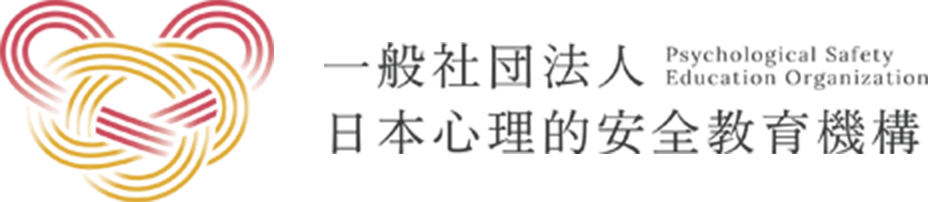




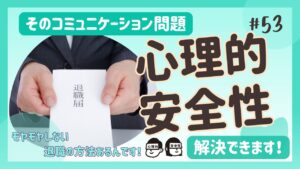
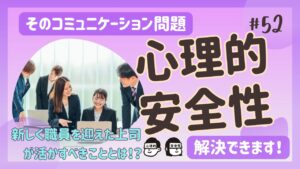

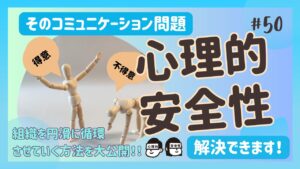
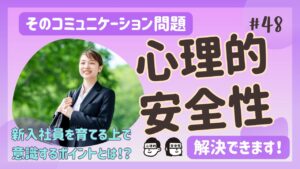
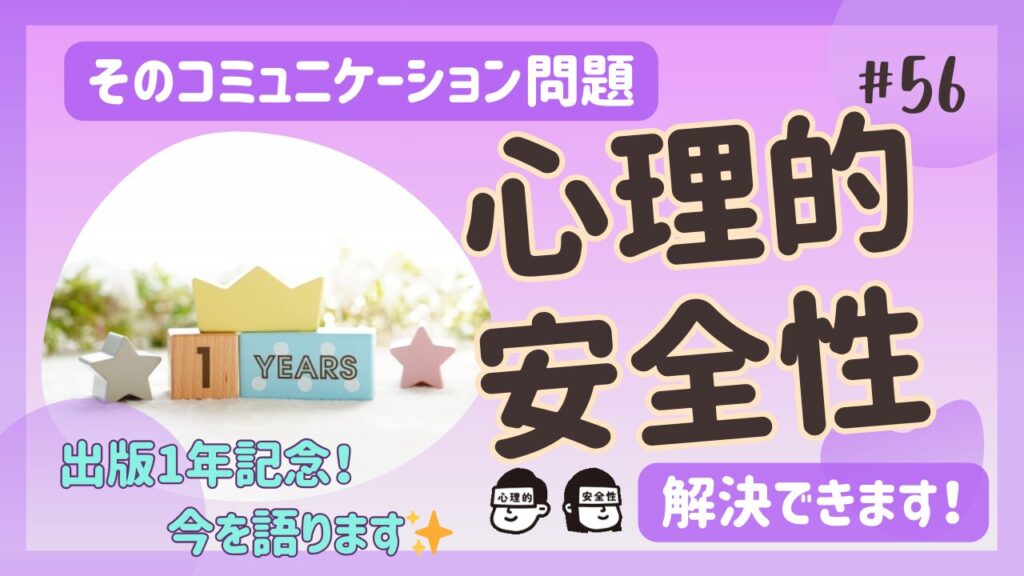




コメント