

前回の配信では、心理的安全性を高める「4つの因子」のうち、
もっとも大切で難しいとされる「話しやすさ」についてお伝えしました。
今回は続編として、「助け合い」と「挑戦できる環境」について掘り下げていきます。
因子②:助け合い 〜誰かが支えてくれるという安心感〜
「助け合い」は、チームの土台を作るうえで欠かせない要素です。
人は一人で挑戦し続けることは困難です。
だからこそ、困ったときに誰かが助けてくれる、支えてくれるという実感は、自信や安心感につながります。
例えば、チーム内で「この作業、苦手なんだよね」と事前に共有されていれば、
得意なメンバーがサッとフォローすることもできます。
このように、不得意なことを話しておける環境=話しやすさが前提となって、助け合いが成立します。
何気ない「手伝おうか?」「分からなかったら聞いてね」といった一言や、ちょっとしたメモでも、
そこには大きな意味があり、チームの安心感と連携力を高めるきっかけになります。
ただし注意したいのは、「何かあったら言ってね」という声かけが形骸化してしまうこと。
いざ困って相談しても「今は無理」と冷たく返されてしまうようでは、信頼関係は築けません。
仮に今は対応できないとしても「今日中は難しいけど、明日なら時間作れるよ」といった伝え方が大切です。
因子③:挑戦できる環境 〜失敗しても大丈夫、だから挑める〜
次に紹介する因子は「挑戦できる環境があるかどうか」です。これは、助け合いと密接に関係しています。
挑戦には安心感が不可欠です。
たとえば、バンジージャンプに挑戦する時、「このロープは10回に1回切れます」と言われたら、飛べませんよね。
でも「絶対に大丈夫、命の危険はない」と保証されていれば、人は恐怖を乗り越えてチャレンジできるものです。
これは職場でも同じです。
「このチャレンジ、失敗したら終わり」と感じるような環境では、人は身動きが取れません。
一方で、「失敗してもチームがサポートしてくれる」「助けてくれる人がいる」と思えると、ぐんと挑戦しやすくなります。
上司と部下の関係性も「対等な人間同士」として見る
挑戦を促す安心感は、上司・部下の関係性にも現れます。
上司が部下に安心感を与えることはもちろん大切ですが、
部下からも「助けますよ」「声かけてください」と働きかけることが、双方向の信頼関係を生み出します。
人間関係の基本は「対等な人間同士」。
年齢やキャリアは違っても、得意不得意、持っている価値観もさまざま。
自分が得意なことで誰かを助け、誰かの得意なことで自分が助けられる。
その循環がチームを強くしていくのです。
他部署や外部の力も「助け合い」
自分たちのチームの中だけで完結しないこともあります。
そんな時は、他部署や外部の専門家にサポートを頼るのも「助け合い」の一部。
自分たちの「へこみ」を埋めてくれるパズルのピースを探すように、
視野を広げて人とつながっていくことが、良いチーム作りのポイントです。
助け合いの第一歩は「声をかけること」から
「今、大丈夫?」「困ってることない?」そんな一言が、助け合いのきっかけになります。
言い方にもコツがあります。
「大丈夫だよね?」と期待を込めた聞き方だと、本当は困っていても「大丈夫です」としか答えられません。
「何かあったら言ってね」と投げるのではなく、
「最近どう?」と気遣いを見せるような聞き方の方が、本音が出やすくなるのです。
また、私が開発した「エモトーク」のような感情を可視化するツールを使うのも効果的。
特に感情表現が苦手な人同士でも、自然に気持ちを伝え合えるきっかけになります。
挑戦は、支え合える関係性の上に咲く
挑戦には、必ず安心感が必要です。
そして、その安心感は日々の「助け合い」や「声かけ」から生まれます。
人が安心してチャレンジできる職場とは、弱さを出しても受け入れてもらえる環境がある職場。
話しやすさ、助け合い、そして挑戦。
この3つは、それぞれが独立したものではなく、しっかりとつながりあっているのです。
次回はいよいよ最後の因子、「新しい価値観を受け入れられるか」について深掘りしていきます。お楽しみに!
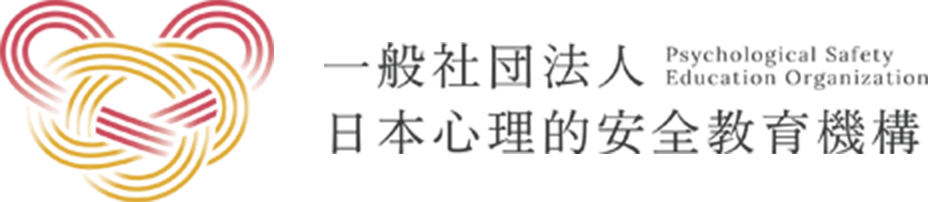




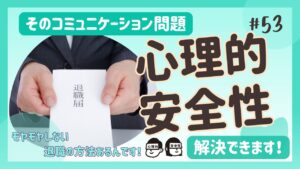
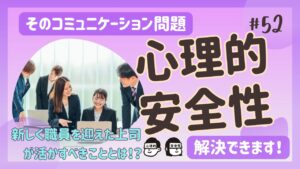

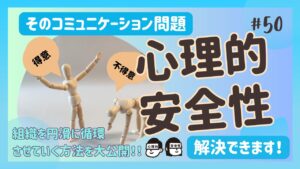

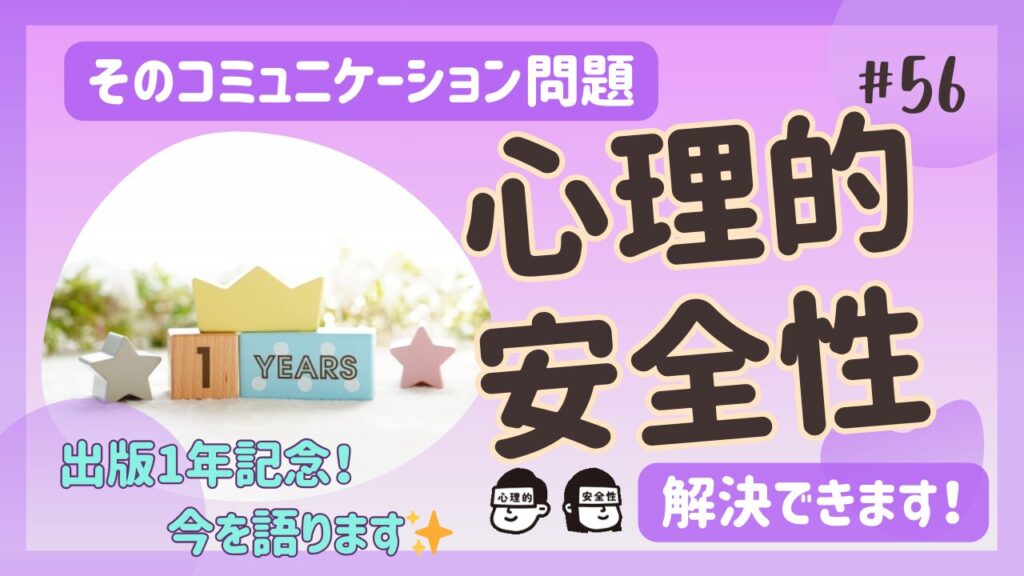




コメント