
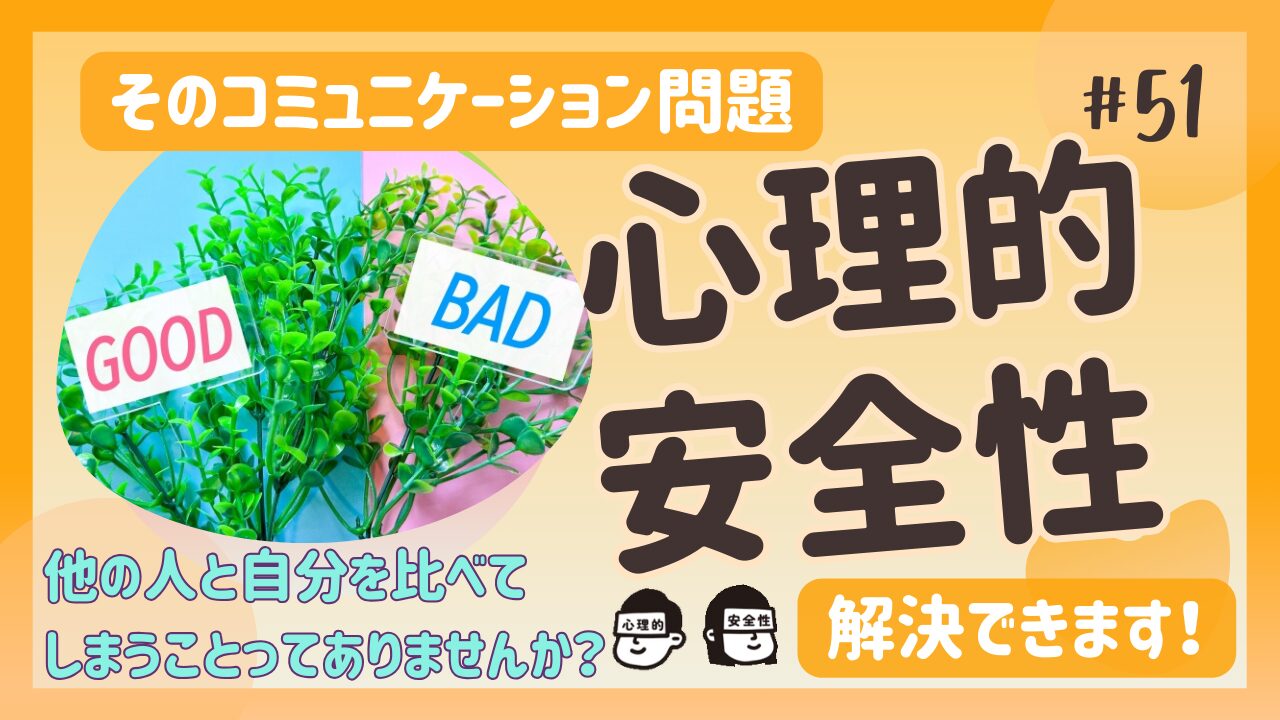
新年度がスタートして1ヶ月。
新しい環境に少しずつ慣れ始めた人も多い頃かもしれません。
でも、この時期に少しずつ増えてくるのが、「あの人はできているのに、私は…」といった“比較”から生まれる不安や焦りです。
私たちは、子どもの頃から「○○ちゃんはできるのに」「お兄ちゃんはもっと頑張ってたよ」など、
意識せずとも比較に晒されながら育ってきました。
社会に出てからも、会社の評価制度や同僚との成績差により、自分の立ち位置を“他人との違い”で測られる場面がたくさんあります。
けれども、そうした比較が生むのは、多くの場合、不安や劣等感です。
中には、自分より業務が遅い人を見て「こんなこともできないの?」と無意識にマウントを取ってしまう人もいます。
こうなると「苦手です」「助けてください」とは言いにくくなり、職場からは心理的安全性がどんどん失われていきます。
では、どうすればいいのでしょうか?
得意と苦手は誰にでもある
どんな人にも、努力しなくても自然とできる“超得意”な3%の力があると言われています。
これは、本人にとっては「呼吸するくらい自然にできること」。
たとえば、ある人は複雑な資料を整理するのが得意かもしれないし、ある人は人前で話すことが苦ではないかもしれません。
私の場合、人前で話すことはまさに“努力していない得意分野”ですが、
郵便物の整理や書類の管理など、細かい作業はとても苦手です。
このように、誰でも「得意なこと」と「苦手なこと」の両方を持っています。
不得意を“隠さない”職場が、安心をつくる
多くの人は、不得意なことを隠そうとします。
「完璧でいないと評価が下がる」と思ってしまうからです。
でも本当に大切なのは、「自分が苦手なことをオープンにできる空気」と「それを補い合えるチーム」です。
ある業務を任せたスタッフが苦戦している様子を見たとき、私はこう声をかけます。
「これやってて、楽しい?」
その一言から「実はしんどかった」という本音が出てきたり、別の業務で才能を発揮できたりすることもあります。
大切なのは、「あなたはダメ」ではなく「別にもっと向いてることがあるかもしれない」と伝えること。
これだけで、相手の自己肯定感を保ちながら適材適所の環境を作ることができます。
言葉選びが心理的安全性を決める
「こんなこともできないの?」という一言は、たとえ冗談でも相手を萎縮させてしまいます。
言い換えの力が大切なのです。
本音をそのまま言葉にするのではなく、「どう伝えたら相手が受け取りやすいか」を考える。
これが“コミュニケーション力”です。
伝え方のバリエーションを持っている人は、まさに対話の達人。
直球だけでなく変化球も投げられるようになることで、チームの信頼関係は格段に高まります。
比較しない、自分のペースを大切に
どんなに完璧に見える人にも、見えていないだけで“ポンコツ”な部分があるものです。
自分が誰かと比べて落ち込んだときは、
「自分の“超不得意”と相手の“超得意”を比べてしまっていないか?」と冷静に見つめ直してみてください。
会社にとって大切なのは、1人のスーパー社員よりも「誰かが抜けても成果を出せるチーム」。
自分の得意を活かしながら、チームに貢献すること。それができれば、比較もマウントも不要な、安心して働ける職場がきっと作れます。
まとめ
・不要な比較は心理的安全性を損なう
・得意と不得意は誰にでもある
・苦手を隠さず、チームで補い合う
・伝え方の工夫で信頼関係を築く
・「自分らしさ」を軸に、のびのび働ける環境を
「苦手なこともあるよね」と素直に言える場づくり、そして「それなら私がやるよ」と言い合える関係性。
それこそが、今の職場に求められている“本当のチーム力”なのではないでしょうか。
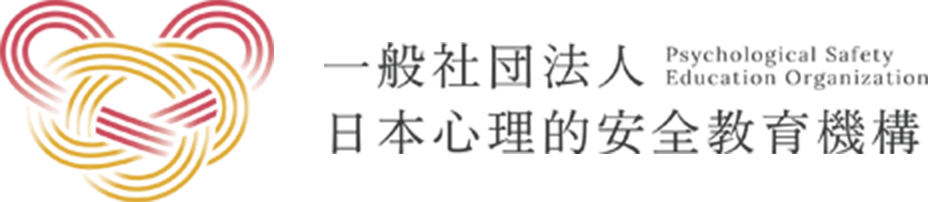




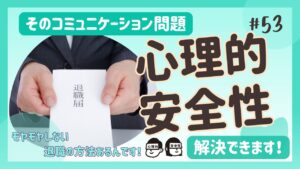
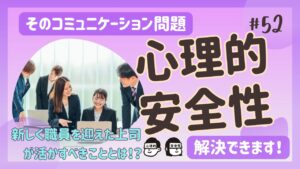
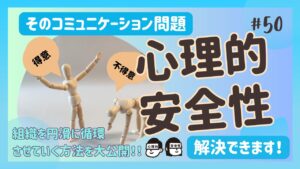

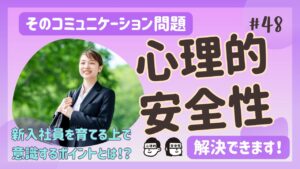
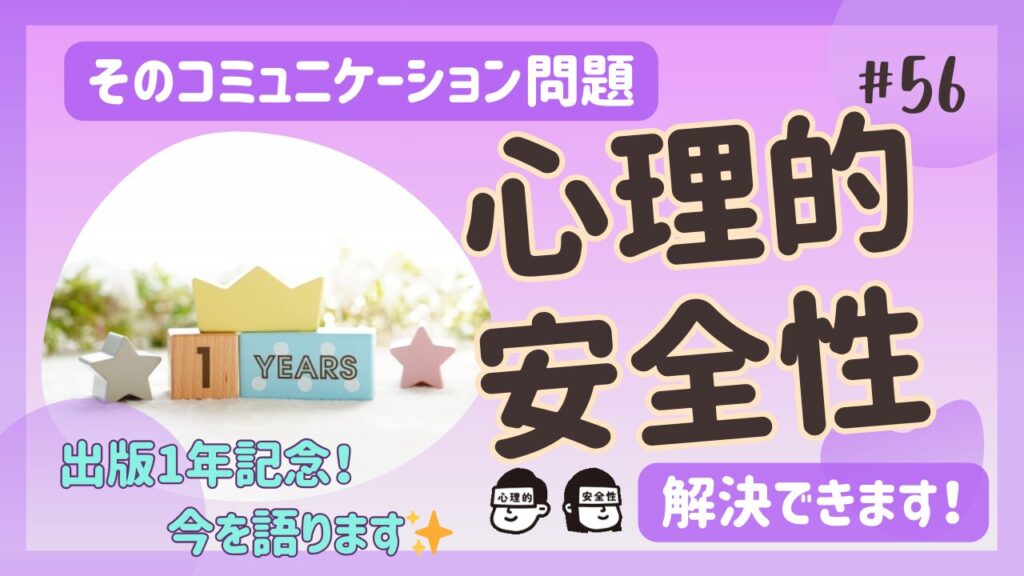




コメント