
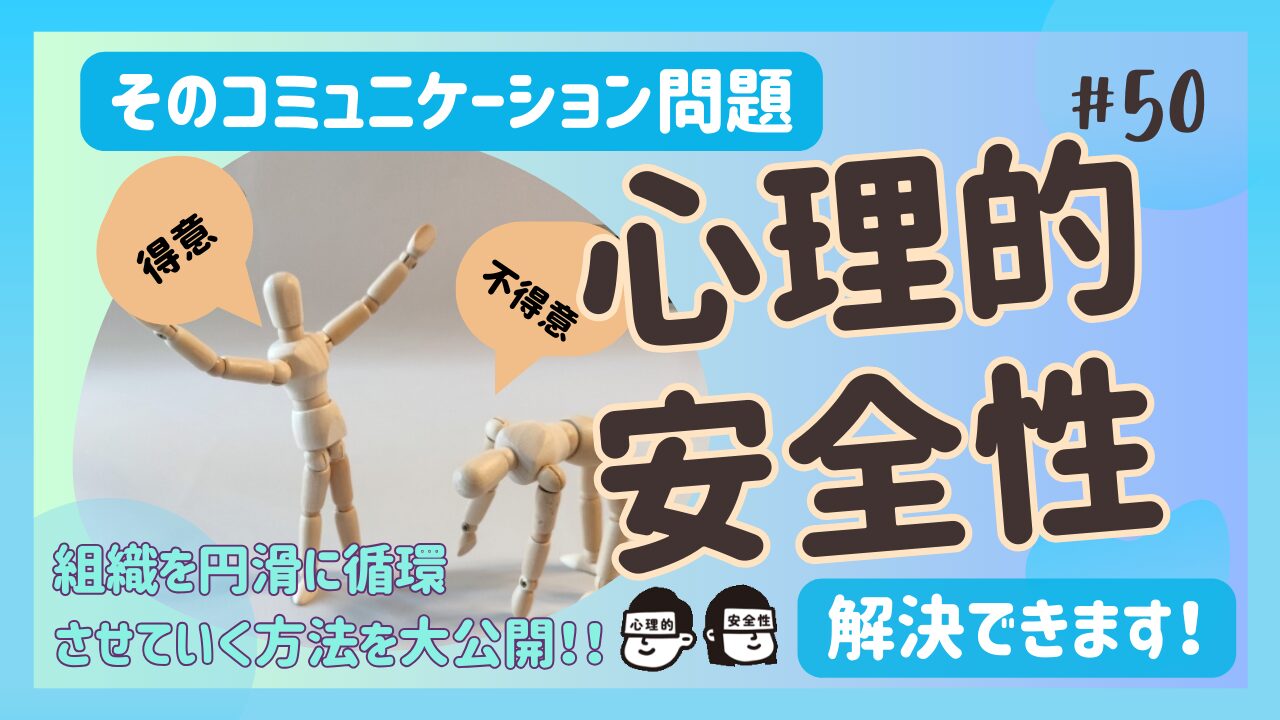
この春で配信開始から1年を迎えるこのコラム。
人間関係の悩みが尽きないように、職場の中でもさまざまな課題が日々生まれています。
今回は節目となる50回目ということで、「苦手なことを手放せる職場作り」をテーマにお届けします。
私たちは「苦手」を隠して育ってきた
日本の教育には、偏差値や通信簿といった「平均点を基準にした評価」が根づいています。
社会人になっても、会社の評価制度はある基準をクリアできているか、という視点で運用されがちです。
その結果、評価の中で「できていない部分=改善すべき点」にばかり目が向けられ、
「苦手なことでも努力して克服すべき」という空気が当たり前のように流れてしまいます。
けれど、人には得意不得意があって当然です。
むしろ、明らかに苦手なことは無理にやらせず、得意を生かすことで組織の生産性はぐんと上がるのです。
苦手は誰かの得意。パズルのように補い合えるチームを
苦手を隠さずに「これは苦手なんです」と言える環境。
そんな雰囲気があるだけで、チーム全体の空気が柔らかくなり、補い合える関係が生まれます。
たとえば
・Aさん「資料作るの苦手だけど、プレゼンは得意です」
・Bさん「話すのは苦手だけど、資料作りなら任せて」
このように役割を分担することで、どちらも苦手を抱えずに力を発揮できるチームができあがるのです。
上司にこそ求められる「苦手なことを聞く力」
職場で「苦手です」と言える空気を作るには、上司の姿勢が大きなカギを握っています。
「○○が苦手」と言った瞬間、「やる気がない」「甘えている」と捉えられてしまえば、誰も本音を口にできません。
だからこそ、上司は最初に**「何が得意? 何が苦手?」と聞くことが重要**です。
そして「苦手なことはやらなくていい。その代わり、得意なことでしっかり貢献してね」と伝える。
これだけでチームの雰囲気は大きく変わります。
「苦手を手放す」は、家庭でも実践していた!
私自身も、実は料理が苦手。
それを無理にやろうとしていた頃は、食材を無駄にしたり、時間も手間もコストもかかってしまっていました。
そこで潔く外注を選択。結果、家庭も仕事もスムーズに回るようになりました。
「やらないとダメ」と思い込むより、「他の誰か、あるいは外注で補えるなら任せてしまおう」
その方が生産性も、気持ちの余裕も、ずっと高まります。
「苦手」こそチームの個性になる
心理的安全性の高い職場では、「苦手」はマイナスではなく、チームで補い合える“個性”として機能します。
逆に、苦手なことを無理にやらせる職場では、生産性もモチベーションも落ちていくのです。
「何が得意で、何が苦手?」
これを聞ける上司、これを言えるメンバー。
そんな関係性が築かれた職場こそ、心理的安全性の高い職場といえるでしょう。
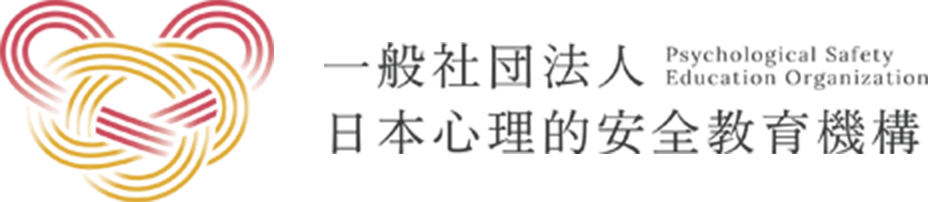




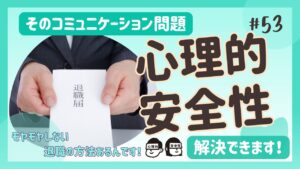
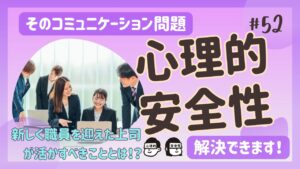


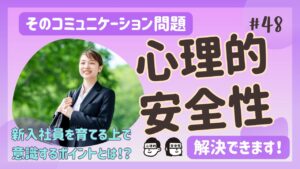
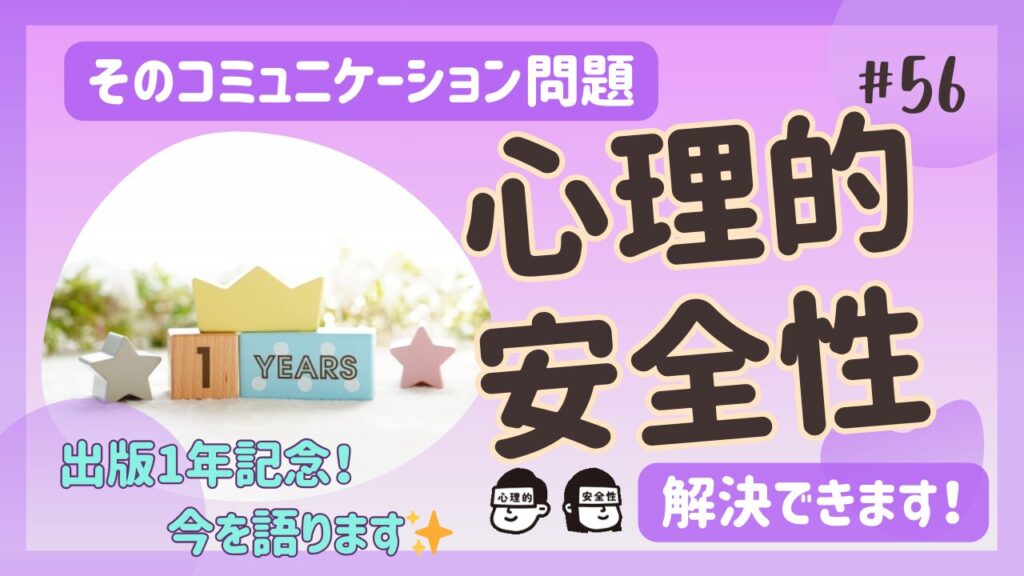




コメント